本を出版するなら─文芸社。「出版」のこと、気軽にご相談ください。
平日9:30〜18:30通話無料
0120-03-1148問い合わせ
検索
書籍検索
フリーワード検索
ジャンル検索
小説
エッセイ
童話・絵本・漫画
画集・写真集
教育
実用
語学
社会
ビジネス
医学・健康
看護・闘病
伝記・半生記
歴史・戦記
詩集
俳句・短歌
地理・紀行
自然・科学・工業・学術
哲学・心理学・宗教
芸術・芸能・サブカルチャー
スポーツ
雑誌・学参・その他
本を出版するなら─文芸社。「出版」のこと、気軽にご相談ください。
平日9:30〜18:30通話無料
0120-03-1148問い合わせ
検索
書籍検索
フリーワード検索
ジャンル検索
小説
エッセイ
童話・絵本・漫画
画集・写真集
教育
実用
語学
社会
ビジネス
医学・健康
看護・闘病
伝記・半生記
歴史・戦記
詩集
俳句・短歌
地理・紀行
自然・科学・工業・学術
哲学・心理学・宗教
芸術・芸能・サブカルチャー
スポーツ
雑誌・学参・その他
Blog
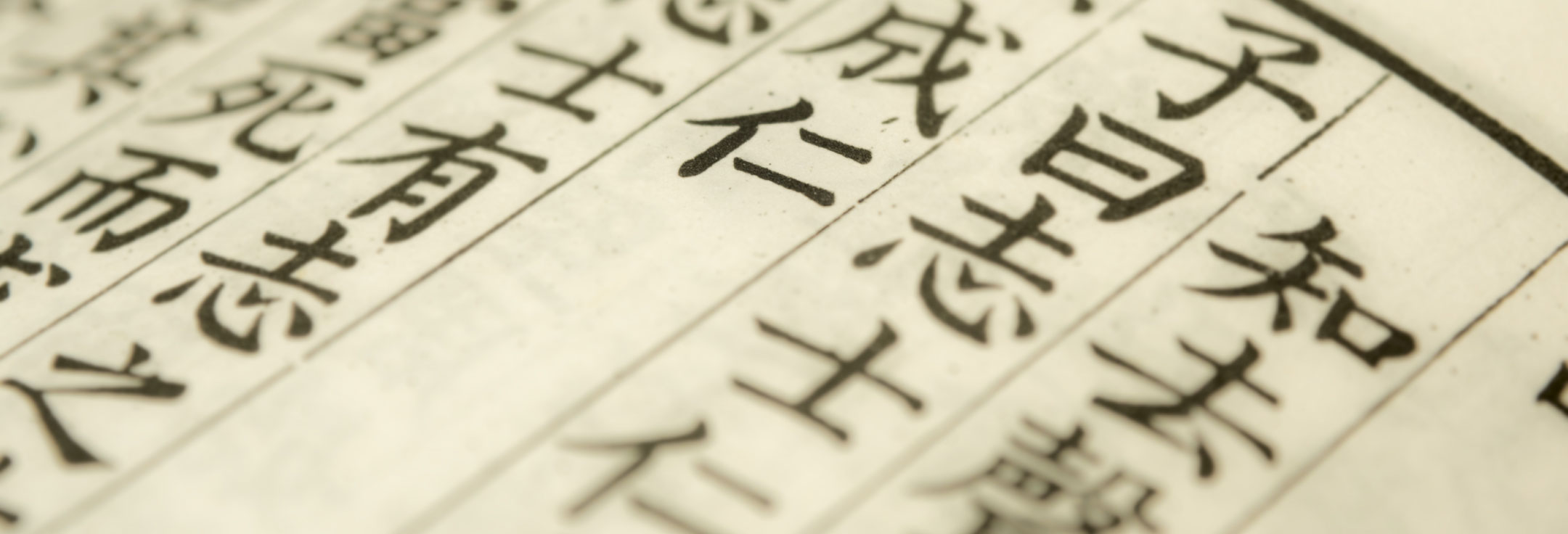
日本人の「死生観」……なんていうとちょっと大仰になってしまうので、もっとシンプルにお訊きしますが、あなたご自身の死生観とはどのようなものですか? え、そんなこと考えたこともないですって? はいはい、いいんですよ。そんなことではダメだというような話ではありませんから。大多数が無宗教を自認する日本人には、何かきっかけでもない限り確たる死生観をもたない方が多いと思われます。ある意味でそれこそが日本人の死生観ともいえ、この国においてはむしろ当たり前のことかもしれません。でも、だからといって誰も彼もが真実無宗教であるかというと、そういうわけではなさそうです。考えてみてください。あなたが仮に無神論者や無宗教を自認・公言しているとして、縁起でもないたとえ話になりますが、近しい人の死を経験したなら、義務感や単なる儀礼的な態度ではなく、真の悲しみと敬意をもって弔い、厳粛なる「儀式」に臨まれるのではないでしょうか? 常日頃は輪廻転生やら極楽浄土やらに関心を払っていなくても、心のなかには確かに、あなたが生まれたときから影響されてきた「宗教」が存在しているものと思います。また、そうした経験をすることで、自分なりの死生観を静かに形成しはじめる方も少なくありません。そのとき、日本は多神多仏の国などとも言われるように、個人の内部でも特定の宗派に深く根ざした死生観ではなく、ありとあらゆる神や仏の死生観を取り込むことになるのかもしれません。
さて、死生観を取り上げた作品は数限りなくありますが、もしあなたがそれを題材に小説を書くとしたら、どのようなものになるでしょうか? 小説ですから当然、そこには訴えるべきテーマがストーリーのなかに内包されることになります。そして死生観を扱う以上、おのずと何かしらの宗教の本質的教義が核となっていくはずです。ご存じのとおり、いにしえより世界にはさまざまな宗教が生まれ、その死生観もそれぞれに異なっています。たとえば、古代エジプトでは、死後再生して永遠の生命を得られるよう、願いを込めて遺体をミイラにしました。キリスト教では来たるべき最後の審判と復活に備え、肉体を燃やさず土葬する傾向にあります。一方、仏教には六道や輪廻転生、縁起といった思想があるため、現世の肉体を留めるこだわりがないとされています。仮に、あなたがいずれの宗教の信仰ももたない人であっても、あなたの書く小説の死生観というテーマには間違いなく、対立的な意味も含めた何らかの形で、いずれかの宗教教義の影響が立ち現れるはずなのです。死生観を題材に小説を書く以上それは不可避なのです。
死生観を小説の上で展開するにあたっては、その営み自体が読者なくして成立しませんので(読者をもたない作品を小説と呼ぶことはできますが)、そこでキーワードとなるのが「共感」です。共感を誘うだけでなく、共感できない感情(=反発)を含めて、読者のそれを自在に操る小説こそが優れた作品であることは間違いありません。書き手は常に読者の共感を意識しながら作品を練ることになります。となると自然、日本人の精神性への理解とアプローチが必要となってくるでしょう。たとえ仏門に入っておらずとも、死者は荼毘に付し、葬儀を営み、墓参もまあまあ欠かさず、仏壇や位牌に祈りを捧げる、日本人の一種独特の精神性です。敬虔な仏教徒でないというのに、これいかに? 単なる慣習に過ぎないのでしょうか? あなたならこれをどう理解、説明するでしょうか? 実は、そこには「孝」を重んじる道徳的心性があります。そしてこの「孝」を本来的に徳としたのが儒教なのです。
日本人の宗教や死生観について考えるとき、すぐに仏教が連想され、戦前はもちろん、戦後もしばらくは影響力を保っていた儒教などは、もはや消え去ったと思われている。しかし、実はそうではない。私たちの宗教感覚の深層には、生命の連続を重んじる儒教が伏流となって流れているのである。
(加地伸行『沈黙の宗教──儒教』/筑摩書房/2011年 筑摩書房Webサイト内容紹介文より)
儒教といえば儒学。学校の授業で習った中国の「孔子」の名を思い出される方も多いのではないでしょうか。また韓国では、儒教が政治や文化に大きな影響を与えてきた歴史的な背景もあり、現在の社会通念にも色濃く反映されています。ただ、具体的にどういうものかと問われれば、親に孝行しろとか目上の人は敬えとか、古くさくて堅苦しい、いかにもなアレかな? と思われる方も少なくないでしょう。が、ここには小さくない誤解があります。儒教には3000年の歴史があるといいますが、主君への忠誠、親に対する子の義務のような考え方は、乱暴にいえば、のちの世が社会にとって都合よい解釈を広め浸透していった結果生まれたようなものなのです。儒教における「孝」は本来、死生観に深く関係しています。『沈黙の宗教──儒教』の著者である加地伸行は、死ねば「亡き親が遺した身体」であるところの遺体を祖先に返し、「己の遺伝子を載せた子孫の肉体が存続する」、すなわち「子孫がつづく」ことによる永遠性こそが「宗教的孝」なのだと説きます。これこそが「生命の連続を重んじる」ということなのでしょう。
儒教は、死によって肉体から分離した魂をもとの肉体とひとつにするのが生死本来の姿──と考えるシャーマニズムを背景にもつといわれています。このシャーマニズムが連綿と受け継がれ、次第に「家族」というミニマムな単位のなかにその精神性が引き込まれることになります。お彼岸ともなれば多くのお寺で仏事が執り行われ、「本家」と言われるようなお宅では供物が捧げられるわけですが、現在のそうした習わしも仏教本来の「輪廻転生」の教えとはそぐわない一面をもっていたりもします。しかしそれは、仏教が儒教の影響を受けたものとして、日本の風土、日本人の心性に浸透した結果だからだといえるのでしょう。
死者を見送る葬儀を営み、墓や位牌に手を合わせる日本人。それは因習でも形骸化した儀礼でもありません。祖先祭祀という教え、信心が、日本人の死生観と精神にフィットしたものである証ではないでしょうか。加地伸行は次のように語っています。
〈死〉こそ宗教の本質を貫くものであると確信した。
であるならば、葬儀を語ってやまない儒教に、宗教の本質があって不思議でない。いや、死という切り口なくして儒教の宗教性を明らかにすることはできないであろう
(Webちくま「高野山での体験から『沈黙の宗教──儒教』文庫化に寄せて」より)
死生観とは、とりたてて意識することはなくとも、誰もが何かしらの形で心にもつもの。題材としてのその世界は広く、思想は深遠です。生きとし生けるもの、死を意識しない生物はいないでしょう。そして私たち人間はそのなかでも「考える葦」。死を本能的な忌避感や恐怖、あるいは消滅としてだけ捉える人などどこにもいません。いつそのタイミングが人生でやってくるかわかりませんが、自分の死が迫ろうとそうでなかろうと、切実に死を考える瞬間は誰にでもやってくるはず。それと同じように、作家や小説家を志すならば、いつか必ず「死生観」をテーマとした作品を書く日が来るはずです。加地曰くところの沈黙の宗教──儒教。それを足がかりに、死生観を語る名品をものするのはあなたかもしれません。
※Amazonのアソシエイトとして、文芸社は適格販売により収入を得ています。
2025/02/19
4
「恐怖」、それは底知れないもの 人間がもつ“人間らしさ”のひとつに、「感情」が挙げられます。動物にだって感情はあるワイ! というご意見 ...
2024/12/06
4
「感情」とは魔物のようなもの 人間とはなんと複雑で面倒くさい生き物であるのか──。こうした問い、というよりはむしろ慨嘆にも似た思いを自 ...
2024/11/22
4
ハリウッドに背を向けるか、あるいは手を結ぶか ハリウッドといえば、映画産業の都。派手なエンターテインメントを生み出す煌びやかな世界。と ...
2024/08/01
4
「描写」は作品の核を宿すものと心得よ 思い切りよく換言するなら、小説はすべて「描写」で成り立っているともいえます。登場人物が和やかに談 ...
2025/04/04
5
ファンタジーと「エブリデイ・マジック」 古くは『ナルニア国物語』、現代でも『ハリー・ポッター』など、ひとたび火が点けば異次元のセールス ...
2025/03/11
5
「自由」って本当にいいもの? ひとくちに「自由」といっても、いろいろな形やイメージがあるわけですが、その根本的な意識・認識は時代ととも ...
2025/02/19
4
「恐怖」、それは底知れないもの 人間がもつ“人間らしさ”のひとつに、「感情」が挙げられます。動物にだって感情はあるワイ! というご意見 ...
2025/02/14
6
「アイデア」とは誰にも等しく“降りてくる”もの 「降りてくる」というのは、近年、ふだん使いが当たり前になってきた言葉のひとつです。もと ...