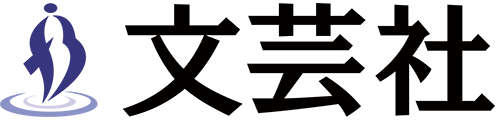�܂��́u�G���X�v�̖{�����l����
�{�����������Ȃ��Ɋւ�炸�A�u�G���v�Ƃ������t�ɐl�͔������܂��B�����Ă��Ȃ��t��������l�قǁA���̎��Ȃɂ��Ȃɂ��H�@�Ȃɂ��u�G���v�ȂH�\�\�Ɖ�R�������𗧂Ă܂��B�}�@�Ȃ�Ă����i�U�}�X�c�c�ƁA���ꌩ�悪���ɔ��ԂɃV������}�_���Ƃė�O�ł͂���܂���B���R�ł��B�t���C�g�́u�G���X�ƃ^�i�g�X�v��l�Ԃ̗~�]�Ƙ_���܂������A�u�^�i�g�X�v���u���Ɍ������Փ��v���Ƃ���A�u�G���X�v���Ȃ킿�u���ւ̏Փ��v�Ƃ́u���̗~�]�v�Ȃ̂ł��B�䂦�ɕK�R�I�ɂƐ\���܂����A���ɂ����̐�����|�p�ɂ����Ă��G���X�͈��e�[�}�ƂȂ�A���w�ł͐������w�ƌĂ��W���������m������Ɏ���܂����BD.H.�������X�w�`���^���C�v�l�̗��l�x�A�W�����E�N�������h�w�t�@�j�[�E�q���x�A�䌴���߁w�D�F���j�x�A�J�菁��Y�w�s�l�̈��x�A�c�S�Z�w�ԂƎցx�A�ʂĂ͌Ñ�C���h�́w�J�[�}�E�X�[�g���x����l�C��Ƃ̐Γc�ߗǁwsex�x�܂ŁA�Í������G���X�����������w��������Ζ����ɉɂ�����܂���B
���R�Ȃ���A�}�`���A��Ƃ��G���X�ɒ��ڂ��܂��B����ł����Əd�˂��鐫���V�[���A���ʂ̐l�X�̓���ɒj���̔�ߎ�������߂����ꂩ��́A�����Ă��邪�䂦�̏Փ��������Ƃ��ĔM���`����Ă��܂��B�����A�G���X�Ƃ͂�͂�l�̐��i�����j�Ȃ̂ł��B�������Ȃ���A�܂��Ƃɐɂ��ނ炭�́A�@�艺����ׂ��ӂ��́u���v�A�܂苝�y�́u�Z�b�N�X�v�Ɛl�Ԃ̖{���ł���Ƃ���́u���i�����j�v���A�o�����X���������������ɂȂ��Ă��܂��Ă���P�[�X���������Ƃł��B�u�E�[�v�u�A�[�v�Ȃǂƚb������̐����V�[�������C���ŏI����Ă��܂��ẮA���w�Ƃ��Ă̌|�p���╨��I������l������͓̂���ł��傤�B�J��Ԃ��܂����A�G���X�Ƃ͐l�Ԃ������Ă��邩�炱�����N����Փ��Ƃ����Ӗ��ł́A�S���▬���Ƃ������������ۂƕς��Ȃ��A�����Ђ�����ɐ��I�ȍs�ׂ�\�����邾���ł́A�S���̓��������X�`�ʂ��邱�ƂƑ傫���ς��͂���܂���B�l�ԂɌ�������悤�ɁA�G���X�̔����ɂ����܂��܂ȗ��R�A������킯�ŁA�����ɓ��ݍ���ł����A�u����v�Ƃ��Ă̐��ʂ□�킢�����܂�Ă���̂ł��B
����������Ƃ��`���A���~�̉ʂĂ̕���
���āA�O�L�̒ʂ萫�����w�͐��������݂��܂����A�j���̐�����`���Ĉꐢ���r�������Ƃ��ẮA�n�ӏ~��́w���y���x��������l�͏��Ȃ��Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�f��ɂ��h���}�ɂ��Ȃ�܂����B�����̒j���̗����A�܂�s�ϊW���ނƂ������̕���́A���~�̉ʂĂɎ�l�������̐S���Ŗ�����܂��B����͉ʂ����āA�s��������������l���m�����ɏ}�����p�ł������̂��A����Ƃ��A�s�������ׂ����čs�����������H�ł������̂��\�\�B
꣎q��m���Ă���A�v�͕K�v�ȏ�ɐl�ڂ�����A�]�v�ȋC����������C�������Ă����B
�i���j
���̊J������̂��������ɂȂ����̂́A1�N�O�A����܂ł̕����E��������āA�������Ƃ����ՐE�ɉꂽ����ł���B
�i���j
�����Ŗ����ɂȂ�`�����X���킵���ȏ�A2�N��ɂ�55�ɂȂ�A���͂�i���ɖ����ɂȂ邱�Ƃ͂��肦�Ȃ��B���Ƃ��������Ƃ��������Ƃ��Ă��A����ɒn���ȃ|�W�V�����Ɉڂ邩�A�q��Ђɏo�����邾���ł���B
�����v�����u�Ԃ���A�v�ɐV���������Ă�����̂��������B
�i�n�ӏ~��w���y���x�p�쏑�X/2004�N�j
�w���y���x�ɂ͔Z���Ȑ����V�[�������x�ƂȂ��`����܂����A���ɖ|�M���ꂽ���ɖ�����l�������̓��ɂ́A����Ș��Â��ł����邱�Ƃ��킩��܂��B�u���y���v�iParadise Lost�j�Ƃ͂��������A�A�_���ƃG���@���G�f���̉���Ǖ�����鋌���̑}�b�ł���A�V�g���V�t�@�[�̍����ɂ��y���������Ă����l�Ԃ̎p���r����17���I�C�M���X�̎��l�~���g���̏������ł��B�w���y���x�Ƒ肳�ꂽ����ŁA��l���Ɂu�V���������Ă�����́v�Ƃ͉��ł������̂��A�Ƃ߂ǂȂ����̊�x���j�łւ̗\�����\�\�\���ꂱ���́A�ޗ��֗����䂭�j����ʂ��č�҂��₢�����Ă��邱�Ƃ�������܂���B
�t�F�e�B�V�Y���ɑN�₩�ȕ����̏�����
�J�菁��Y�̒Z�ҏ����w�h�x�́A�h�t�̒j�����z�̑��Ɣ���������f�v���h���{������ł��B���̍�i�ɐ�����ʂ͂ЂƂ��o�ꂵ�܂��A�j�̎��X�ȃt�F�e�B�V�Y���ɂ̓G���X���Ïk���āA�d�������r�Ȉ��̐��E�����o�����Ă��܂��B
���̏��̑��́A�ނɂƂ��Ă͋M�����̕�ʂł������B�d�w����N���ď��w�ɏI��@�ׂȌܖ{�̎w�̐������A�G�̓��̊C�ӂŊl��邤���ׂɐF�̊L�ɂ����ʒ܂̐F�����A��̂悤�����̂܂閡�A�����Ȋ�Ԃ̐����₦����������Ƌ^����畆�̏���B���̑������́A�₪�Ēj�̐����ɔ삦����A�j�̂ނ�����D�݂��鑫�ł������B
�u�e���A���͂��������̂悤�ȉ��a�ȐS���A�����Ǝ̂āT���܂��܂����B�\�\�\���O����͐^��Ɏ��̔엿�ɂȂ����˂��v
�ƁA���͌��̂悤�ȓ����P�������B���̎��ɂ͊M�̂̐����ЁU���ċ����B
�u�A��O�ɂ�����ՁA���̎h�������Ă���v
���g�͂����]�����B
���͖ق��������Ĕ���E�����B�܂��璩�����h�̖ʂɂ����āA���̔w�͎WࣂƂ����B
�i�w�h�x/�w����Y���r�����X�T�@�����Z�ҏW�x����/�������_��/1998�N�j
�w�h�x�͂����Z������ł����A�ق�̂킸���̒o�݂��Ȃ��A�I�n�����߂�悤�ȋٔ����������A���I�|���ɓM���j�̓��ʂ�Z���ɕ����яオ�点�Ă��܂��B���̏����ł���ɒ��ڂ��ׂ��́A�j���̐����Ƃ����܂����A�j�̔S���I�ȋC���Ə��̂����Ƃ��������̂Ȃ����A�ۗ������ΏƂƂȂ��ĕ`�o����Ă���_�ł��B�����Ŗ��炳��h�荞�܂ꂽ�����h�̔w�ɒ����𗁂тė����X�g�́A�J��̏����ς̈�[���f������̂Ƃ����Ă悢�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�G���X��[����������m�[�x�����w�܍�Ƃ̎����
�m�[�x�����w��܍�Ƃ������A�������u���v���e�[�}�ɂ�����i�\���Ă��܂��B��]���O�Y�́w���I�l�ԁx�Łu���I�l�ԁv�ƂȂ邵�����͂Ȃ��}���Љ�Ő�����N�̏h����`���܂����B��[�N���́w���������x�ŁA�S���̏����Ƃ����Y���Q�����邾���́u�閧����ԁv�ɒʂ��V�l��������ɂ��܂����B�i����Ӗ��g��ܖ����h�Ƃ����Ă������j�O���R�I�v�́A���́w���������x�Ƃ�����[��i���f�J�_���X���w�̌���ƕ]���Ă��܂��B
���̉Ƃɗ��ĕ��̂���J�����V�l�ǂ��̕��Q���A�]���͍��A���̖��炳��Ă�鏗�z��̏�ɍs�ӂ̂��B���̉Ƃ̋�����Ԃ�̂��B��x�Ƃ��̉Ƃɗ����Ȃ��̂͂킩���Ă��B�ނ��떺�̖ڂ����܂����邽�߂ɍ]���͂��炭�������B�Ƃ��낪�������A�����܂��A�]���͖��炩�Ȃ��ނ��߂̂��邵�ɂ��ւ���ꂽ�B
�u���B�v�Ƃ�����ł͂Ȃꂽ�B�����݂��ꓮ�������܂����B�Ƃ��ɂ�߂����Ƃ����A���ǂ낫�̕����傫���₤�����B
���点��ꂽ���̂��炾�ɂ����炭������Ђ͂Ȃ����炤�B�������ߎE���Ă��܂ӂ��Ƃ��Ă₳�������炤�B�]���̒��肠�Ђ͔����āA��Â��������Ђ낪���B�߂��̍��g�̉��������̂₤�ɕ�����B���ɕ��̂Ȃ����������B�V�l�͈Â��C�̖�̈Â�����v���B
�i��[�N���w���������x�V����/1967�N�j
��[�N���́A���Ǝ��̋��E���Ӗ�����u���E�v���e�[�}�ɉ��삩�̏����������Ă��܂����A�w���������x�͂��̌n���ɘA�Ȃ���ł��B���h���ƌ����Č����Ď����̂��̂ɂ͂ł��Ȃ����������́A���ɂ����ē����ʂ��́A�]��ł͂����Ȃ����̂̏ے��ł��傤���B���ƁA���ƁA���\�\�B�܂������G���X�́A�[���ȕ���́u�j�v�Ƃ��čl���[�������Ă����ׂ��e�[�}�Ƃ����܂��B�V���킸�A�j������킸�A��n�D�������Ė�킸�A����ł��Đ[�@����ł���B����قǂ܂łɖ{�������̂ɂӂ��킵���f�ނ́A�Ȃ��Ȃ�����܂���B�l�Ԃ̕��ՓI�ȉc�݂ł������A����y�ȁu�G���v�͂������璆�ɎU�����܂����A�����������ƌ��߂����Ȃ��ł���A�����ɐ��⎀�A�l�ԑ��݂ɓ��ݍ��ސj�H��T�邱�Ƃ������߂��܂��B���ւ̗~�]���s�����ʂ悤�ɁA�G���X�ɂ͌���Ȃ�����̖G�肪�����Ă���ƐM���܂��傤�B
��Amazon�̃A�\�V�G�C�g�Ƃ��āA���|�Ђ͓K�i�̔��ɂ������Ă��܂��B