本を出版するなら─文芸社。「出版」のこと、気軽にご相談ください。
平日9:30〜18:30通話無料
0120-03-1148問い合わせ
検索
書籍検索
フリーワード検索
ジャンル検索
小説
エッセイ
童話・絵本・漫画
画集・写真集
教育
実用
語学
社会
ビジネス
医学・健康
看護・闘病
伝記・半生記
歴史・戦記
詩集
俳句・短歌
地理・紀行
自然・科学・工業・学術
哲学・心理学・宗教
芸術・芸能・サブカルチャー
スポーツ
雑誌・学参・その他
本を出版するなら─文芸社。「出版」のこと、気軽にご相談ください。
平日9:30〜18:30通話無料
0120-03-1148問い合わせ
検索
書籍検索
フリーワード検索
ジャンル検索
小説
エッセイ
童話・絵本・漫画
画集・写真集
教育
実用
語学
社会
ビジネス
医学・健康
看護・闘病
伝記・半生記
歴史・戦記
詩集
俳句・短歌
地理・紀行
自然・科学・工業・学術
哲学・心理学・宗教
芸術・芸能・サブカルチャー
スポーツ
雑誌・学参・その他
Blog
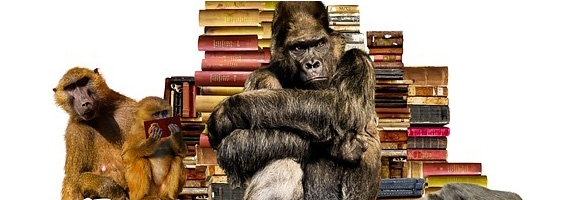
タイトルの「リロン」はもちろん「理論」の意。なぜカタカナか? 画数の少ないカタカナの字面で堅いテーマのハードルを下げてみた、という騙し絵みたいな魂胆があるのではなく、「理論」的な四角四面さとは断然異なる、「リロン」的な柔らかな姿勢で「文学」に歩み寄る方法を探してみよう――と、そういう試みを提示したいからなのです。
エンターテインメント小説ならいざ知らず、純文学となると尻込みしておいそれと手が出ないという人は少なくないはず。理由は至って簡単、「難しい・わからない・面白くない」の三重苦の枷を負うのが、純文学入門者の宿命だからなのです。けれど、これは小説を書くほうにとっても読むほうにとっても不幸なこと。優れた純文学作品には上質な衣をまとうようにして珠玉が具わっているものです。それこそ読者にとって受け取る価値のある財貨なのですから、「難しい・わからない・面白くない」で避けて通っていては、これほどもったいないことはないでしょう。
では、「難しい・わからない・面白くない」が、思い込みの読まず嫌いに過ぎないとしたらどうでしょうか。文芸作品の心髄、芸術性に触れられるメソッド的「文学リロン」があるとしたら、あなたはそれでも素通りして純文学にまだ背を向けますか?
三ツ星レストランのシェフが味音痴であるはずがないように、そもそも優れた詩や小説を書きたいと心する人は、優れた詩や小説を判じる力をもっていて然るべきでしょう。文学を読み解く力を培うのは、知識、経験、センスといったところですが、これらはいずれも積み重ね磨くことのできるものです。経験はあとからついてくる。センスは知識と経験によって研磨されるものである。となると大切なのは知識、これすなわち文学理論です。「リロン」じゃなくてやっぱ「理論」かよ話が違う! と早飲み込みしないでください。何もポスト構造主義を知るためにジャック・デリダを死ぬほど読めとご案内するわけではございません。ただ、先達が遺したレジェンド的作品群としのぎを削るとなれば、やっぱり無手勝流というわけにはいきません。“型”はどうしたって必要でしょ? ですからまず「理論」から、「リロン」に至る話をしようというのです。
人間は文化のみに生きるにあらず。大多数の人間はその歴史を通して、文化に接するチャンスすら奪われてきたのであり、そして現在文化的活動を職業としている幸運な少数者たちの生活を保証しているのも、文化に接することのない人びとの労働である。この単純だがもっとも重要な事実から出発し、この事実をその活動のなかで心にとめておかないような文化理論や批評理論は、いかなるものにせよ、私の意見では、存在するに値しない。
(テリー・イーグルトン著/大橋洋一訳『文学とは何か』岩波書店/2014年)
イギリスの哲学者・文芸批評家のテリー・イーグルトンは、その著書『文学とは何か』で近現代の文学理論を通覧しつつ、「文学」とこれを読み解く「方法論」を結びつける試みを行いました。結果、イデオロギーのない公正無私な文学理論は存在しないと結論づけたのです。
オイオイないのかよ……とうなだれるには及びません。イーグルトンは世の文学理論・批評をメッタ切りにしましたが、そうした理論は端から用いる価値もないといっているわけではありません。つまり、それぞれにイデオロギーを内包する理論の“ひとつ”ですべての小説を読解することなどできはしない、そういっているのです。それは裏返せば、文学理論はその方法論を理解しさえすれば適切に用いることが可能である、ということ。構造主義にもポストコロニアル主義にもそれに相応しい小説がある、だから、ナンバーワンの文学理論は存在しないけれど、それぞれの形と弱点を知ることは決して無駄ではない――『文学とは何か』はそのことを教え、「理論」の中から「リロン」を見つける手助けをしてくれる稀有な一冊なのです。
突然ですが、あなたは嫌いな人と永久(とわ)の契りを結ぼうという気になれますか? ちょっとその気にはなれませんよね(永久の契りを結んだ人が嫌いな人に変わることはままあれど……)。愛なきところに理解なし、文学と密接な関係を結ぶためには、文学への愛が絶対的に必要です。へっ、俺は愛に不器用なのさと地平線の向こうを見つめるあなた。ニヒルを気取っていてはなかなか文学とお近づきにはなれませんが、そんな不器用なあなたにも、文学に対する姿勢、愛し方を教えてくれる格好の書物があります。恋愛の指南書をレジに運ぶのはちと気が引けるものですが、こちらであれば鼻高々にレジ係の女性店員に差し出せます。
『ナボコフの文学講義』の著者ウラジーミル・ナボコフは『ロリータ』で有名なロシア人作家。本書は、ロシア革命後に亡命したナボコフが1940年代にアメリカの大学で行った講義内容をまとめたものです。18世紀から20世紀までの名作といわれる文芸作品を取り上げ、いわゆる文学論・文学批評論ではなく、ナボコフ流の“読み方”を、微に入り細を穿ち情熱を込めて伝授して、学生たちの食い入るような視線を集めた熱い講義であったと想像されます。
さて、上記10項目は、ナボコフがよき読者になるための条件を4つ選びなさいと学生たちに投げかけた問題です。2〜4あたりを選ぶ学生が多かったようですが、ナボコフによる正解は7〜10の4つ。そしてこの姿勢で臨む小説の理想的読み方とは、「ディテール」へのこだわりでした(無類の蝶好きのナボコフらしい視点です)。たとえば、ジェーン・オースティンの小説では作中の女性たちのえくぼについて滔々と語っていて、その熱を帯びた口調は文学への愛と、そんな愛を育てるための文学への接し方を教えてくれるものです。ナボコフはまた、本物の小説とは繰り返し読むに堪える作品であると定義づけています。もちろん馴れ合いではなく、再読する度に新しい発見を与えてくれる、そんな小説との出会いが「読み方」を深めてくれるのだと理解できます。
私が願ったことは、小説を読むのは作中人物になりきりたいというような子供じみた目的のためでも、生きる術を学びとりたいというような青二才めいた目的のためでも、また一般論にうつつをぬかす学者然として目的のためでもない、そういう良き読者にきみたちをつくりたいということだった。小説を読むのはひとえにその形式、その想像力、その芸術のためなのだと、わたしは教えてきたのである。きみたちが芸術的な喜びと困難とを分かちもつようにと、そう教えてきたのである。
(ウラジーミル・ナボコフ著/野島秀勝訳『文学講義』河出書房新社/2013年)
ナボコフは断言します。「読書は頭でするものではない、背筋でするものだ」と。背筋で感じるぞくぞくとする戦慄こそ、正真正銘の感動なのだ――と。本書が取り上げている、オースティン、ディケンズ、カフカ、プルースト、ジョイス……といった名作の古典的ラインアップにも注目しておきたいところ。だって、一流ど真ん中の文芸作品なんて、若き日の読書機会を逃してしまえばそうそう手に取る気になどなれないではありませんか。要するに、誰でもが文学部の学生となってナボコフ先生の魅力的な授業を聴講し、文学史に燦然と輝く名作をじっくりと鑑賞し、「文学リロン」を身につけられる、二度も三度も美味しい極上の一粒――というのが本書の正体なのです。最後に本書から、「文学」の核心に触れる暗示的な一節を。
文学は、狼がきた、狼がきたと叫びながら、少年がすぐうしろを一匹の大きな灰色の狼に追われて、ネアンデルタールの谷間から飛び出してきた日に生まれたのではない。文学は、狼がきた、狼がきたと叫びながら、少年が走ってきたが、そのうしろには狼なんかいなかったという、その日に生まれたのである。
(同上)
名作・優れた作品を読み解く「文学リロン」は、創作のための糧にもスケールにも、そして武器にもなるもの。みずからの創作を高めていくということは、文学の芸術性への理解を深めていくことです。そのための少しの努力を怠ってしまっては、作家になる夢など到底叶わないと、夢を抱きつづけているあなたならわかっているはずです。杓子定規、頭でっかちな「理論」ではなく、愛ある「リロン」を身につけて、一日も早く「芸術的な喜び」を味わおうではありませんか。それは作家になる道程に欠かせない経験でもあるのですから。
※Amazonのアソシエイトとして、文芸社は適格販売により収入を得ています。
2025/04/17
4
「死生観」──さて、あなたはどう描く? 日本人の「死生観」……なんていうとちょっと大仰になってしまうので、もっとシンプルにお訊きします ...
2025/02/19
4
「恐怖」、それは底知れないもの 人間がもつ“人間らしさ”のひとつに、「感情」が挙げられます。動物にだって感情はあるワイ! というご意見 ...
2024/12/06
4
「感情」とは魔物のようなもの 人間とはなんと複雑で面倒くさい生き物であるのか──。こうした問い、というよりはむしろ慨嘆にも似た思いを自 ...
2024/11/22
4
ハリウッドに背を向けるか、あるいは手を結ぶか ハリウッドといえば、映画産業の都。派手なエンターテインメントを生み出す煌びやかな世界。と ...
2025/04/17
4
「死生観」──さて、あなたはどう描く? 日本人の「死生観」……なんていうとちょっと大仰になってしまうので、もっとシンプルにお訊きします ...
2025/04/04
5
ファンタジーと「エブリデイ・マジック」 古くは『ナルニア国物語』、現代でも『ハリー・ポッター』など、ひとたび火が点けば異次元のセールス ...
2025/03/11
5
「自由」って本当にいいもの? ひとくちに「自由」といっても、いろいろな形やイメージがあるわけですが、その根本的な意識・認識は時代ととも ...
2025/02/19
4
「恐怖」、それは底知れないもの 人間がもつ“人間らしさ”のひとつに、「感情」が挙げられます。動物にだって感情はあるワイ! というご意見 ...