本を出版するなら─文芸社。「出版」のこと、気軽にご相談ください。
平日9:30〜18:30通話無料
0120-03-1148問い合わせ
検索
書籍検索
フリーワード検索
ジャンル検索
小説
エッセイ
童話・絵本・漫画
画集・写真集
教育
実用
語学
社会
ビジネス
医学・健康
看護・闘病
伝記・半生記
歴史・戦記
詩集
俳句・短歌
地理・紀行
自然・科学・工業・学術
哲学・心理学・宗教
芸術・芸能・サブカルチャー
スポーツ
雑誌・学参・その他
本を出版するなら─文芸社。「出版」のこと、気軽にご相談ください。
平日9:30〜18:30通話無料
0120-03-1148問い合わせ
検索
書籍検索
フリーワード検索
ジャンル検索
小説
エッセイ
童話・絵本・漫画
画集・写真集
教育
実用
語学
社会
ビジネス
医学・健康
看護・闘病
伝記・半生記
歴史・戦記
詩集
俳句・短歌
地理・紀行
自然・科学・工業・学術
哲学・心理学・宗教
芸術・芸能・サブカルチャー
スポーツ
雑誌・学参・その他
Blog
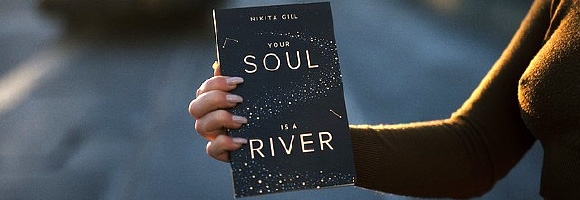
「自分史」を書く。己の人生記を書きたい気もちが芽生えるとき。それは人生の大きな山を乗り越えたひとつの節目であるのかもしれません。人はなぜ、自分史を書きたいと思うのでしょう。書いたことがある、あるいは書いているかどうかは別として、自分自身の人生をひとつの「物語」として眺めたことがある方は決して少なくないはずです。加えて、その人生に苦労が多ければ多いほど、乗り越えてきた峠が険しいほど、記録として残しておきたい、誰かに知ってもらいたいとの思いに駆られるのかもしれません。そして、できれば読んだ人の心に残るような作品であってほしい、そう願うのではないでしょうか。その願いとは、昨今SNS周辺で多くの人が揶揄交じりに口にする「承認欲求」呼ばれるものかもしれません。が、それは、そもそも誰もがプリミティブな領域にもつ「自己肯定」に根差す大切な心理です。
ところが、本来温かく迎えられるべき「大切な心理」の発露を、残念な結果に終わらせてしまうケースがあとを絶ちません。その原因のひとつに、自分史をあくまでも個人的記録として書いて終わらせてしまう人が多いことが挙げられます。いやいや、私など平々凡々の一生で他人様に読んでいただくようなことは何ひとつ……、と謙虚に尻込みする人も少なくありません。しかし、実のところそれは心得違いの発言。自分史が第三者の鑑賞に堪えるか否かは、平凡か非凡かの人生の内容に関わるものではないのです。それを決めるのは「自分史の書き方」。つまり、自分史をどのように綴るのか――のスタンスによって、あなたの自分史が“読めるもの”になるか否かが決まるのです。
自分史とはあなたの人生の縮図。本としての形を留めるようならば分身ともいえます。であれば、多くの人に感銘を与える作品になったほうがいいではないですか。自身の生きた証を家族や知己に残したい云々……と書きはじめられた瞬間、十中八九その作品は、心情的・洞察的深度のない「私的な記録」として留まることになります。でもですよ、ひとりの人間の「人生の証」ですよ! なぜもっと活き活きとした、読む者の心を動かすようなドラマが描かれないのでしょうか。かくして「いやいや、だから私など平々凡々の……」とのコメントに回帰するわけですが、より精彩豊かな自分史を書いていただくためにも、あなたの辞書にある「平凡」という言葉の意味から改めてもらうことにしましょう。
いまこの時代における「平凡」という語は、「見るものがない」「つまらない」と遜る(へりくだる)意味合いよりも、「平凡な日常の幸せ」というように波風の立たないありがたさを慎ましやかに表現する語――と解釈したほうが、よほど気もちにも風潮にもフィットするように思えます。そもそもひとつの波風もない人生なんてないわけで、さらには誰かほかの人と同じ人生なんてものはもっとないわけですから、「平凡な人生」という言葉自体、もはや古臭い美徳精神の名残でしかありません(と言い切っておきます)。つまり、もとより同じドラマはひとつとしてない人生記を、無味乾燥な記録に終わらせてはもったいない、ということなのです。では、精彩に富んで読み手に感動を呼び起こす自分史を書くにはどうしたらよいでしょうか。
繰り返しますが、まず「自分史を書く=個人の歴史的な記録をまとめる」という直線的な考えを捨て去るところからはじめます。そのうえで言います。自身の年表を書き起こしましょう。年表といったら記録じゃないかッ! とここで鼻息を荒くし血圧を上げたあなた、短気は禁物です。自分の歴史を表にして“見える化”するというのは、自分史執筆ノウハウの多くに挙げられているとおり、自分史を書く前に必須の当たり前かつ理に適った作業なのです。小説を書く際に用いられることもありますが、年表起こしとは、人生すなわちストーリーを各パートに分けることで素材化し、そのそれぞれが人生全体のなかでどのような意味をもったのかを定義づける作業なのです。たとえばあなたの青春とは、単に青春期に相当する期間を指し示す以外に、これまでの人生全体を象る上で何かしらの“意味をもった時間”であったはずです。年表を書くというのは、このように過ごしてきたそれぞれの時代を全体の流れのなかで確かめつつ、具体的なイメージを呼び起こす作業になります。自分史づくりの上では、バランスよくメリハリの利いた作品に仕上げるための欠かせないステップです。
さて、年表をつくり終えたら、じっと目を閉じ静かに「いまの自分」に思いを巡らせてみましょう。ひたすら人生を歩いてきたあなたがいまの自分の心に“何”を見るか、それが“記録”以上のドラマティックで濃密な自分史・人生記とするための大事なポイントになります。もし、あなたが現在の生活に平穏を感じているなら、その心境に至らせたものは苦難多き道程であったはず。もし、あなたの胸に配偶者の思い出が宿っているなら、ともに過ごした時間こそが重要な意味をもっているはず。もしあなたがボランティア活動に生き甲斐を感じているなら、そこに導いた根本的な理由が過去に存在するはずです。年表に解説を加えたような自分史を脱し、この世にただひとつの物語として書き上げるためには、自分自身を深く見つめ考えること。そして、現在の生身の自分のあり方と心境に通じる道筋を見つけ出し、その部分にスポットライトを当てて「人生の要」として示すことです。この執筆スタンスこそが、人生を無二のドラマとして読み手の胸に深く刻む、そんな自分史作品を仕上げる第一の秘訣です。
「自分の歴史」であるからといって、自分が生まれてから現在までの来歴を順序立てて記すもの、と決めつけるべきではありません。それこそ年表で事足ります。温もりと躍動感のある自分史を書くために、人生の道のりを改めて振り返り考えるということは、言い換えれば己の輪郭をはっきりと浮かび上がらせる作業であり、その人生を包括してひとつの意味と成果を見出すことにもつながります。それは、生まれてから現在に至る足どりを同じ筆加減で再現しては埋もれてしまう「意味」であり「成果」なのです。
少年時代には親の溺愛から、十六歳頃からは家計の補助に、三十歳近くからは家庭と両親の世話で身動きできなかった。私に面白い青春があるわけではなかった。濁った暗い半生であった。
(松本清張『半生の記』新潮社/1970年)
松本清張は、自伝『半生の記』でみずからの貧しくみじめな半生の足跡を回顧しました。その半生とは、成功に至る希望の明るさなど微塵も感じさせない、ただ耐え忍び懸命に生きた道程でありました。
小倉の町に文学運動が起ころうと、老舗の旦那の芸者遊びの噂が伝わろうと、私にはなんの関係もなかった。よれよれのズボンをはき、下駄ばきで弁当箱をさげて印刷所に通っている私を誰が相手にするであろうか。
(同上)
当時、松本清張は27歳。周囲に蔑まれる不遇の時代はなお10年あまりつづきます。この『半生の記』、出版社からは「小説家になるくだりまでを書いてほしい」との注文がつけられていたといいますが、清張はそれを断って『半生の記』を「濁った暗い時代」に終始させることを貫きました。鬱屈した心境と眼差しを長年もちつづけ、学業・職業で差別を受けた作家は、その異色の経歴がのちの「清張作品」を生む基盤となったこと、その時代の経験こそが「自分の歴史」と呼ぶにふさわしいものと承知していたのではないでしょうか。単なる成功譚にはせず、そこに至るまでの道程を取り上げ描いてみせた清張。著名な作家の自伝とはいえ、「みずからの人生を如何に描くべきか」という考え方は同じです。この執筆スタンスにはおおいに学ぶべきものがあります。
作家に限らず、成功に至るまでの苦難の道を自伝に綴る著名人・成功者は数多います。それは「自分史」というよりビジネス書寄りの啓蒙的な意味づけをされることも多いのですが、本来この領域は著名人にのみ許されている執筆ジャンルではないはずです。無論、安易で身勝手な自堕落人生記が反面教師以上の価値などもちようもありませんが(放蕩記と呼べるまで突き抜ければそれはそれでアリですが)、社会的な成功や知名度に比例して、人生の重みや質が変わるわけでは決してないはずです。ならばあなたの人生が「成功」とは無縁であったとしても、複製品のような顔をして一介のサラリーマン人生を歩んできたのだとしても、あなたには自分史が書ける、しかも“読める自分史”が――と断言しておきましょう。
私の10代は大戦争の真っ最中。私も含め国民の大部分が戦争万歳でした。決して一部の指導者が引きずったんじゃない。民衆が戦争を担い、焦土を招いた。なぜなのか。なぜあなたは、私は、あの無謀な戦争を疑わず支持したのか。一人ひとりの自分がそのとき何を考え、何をしたのかを問う学問が必要だと思いました。そこから歴史に対する反省と個人の責任が出てくる。それが自分史の出発点でもあります。
(『朝日新聞』2010年11月2日夕刊)
「自分史」という言葉の生みの親は歴史家の色川大吉とされています。個人の歴史は民衆史として同時代の歴史を映しだすもの――という視点を提示し、自分史執筆を提唱しました。一庶民が歴史に参加とは大げさだ、などと思うなかれ。歴史を真につくってきたのは指導者・権力者ではなく無名の民衆の力なのです。
同じインタビュー記事で色川氏はこうも語っています。
単なる回想記でも自分勝手なものでもだめ。自分自身を客体化し、同時代の動きや環境とセットにして書かなきゃいけない。詳細な日記を提示して事実だったと実証せねば。しかも、自分を取り巻いていた状況が、自己の内面に深く食い込んだ部分を核としないと本当の自分史にならない。歴史を自分の外にあるものとせず、心の内側に突き刺さり、そこでスパークしたものを書く。
(同上)
色川氏が謳うこの意識を携えること、そして自分らしい自分史とは何かという問いへの深い考察が、輝かしい個人の歴史を書き上げるための極意といえそうです。自分史を書きたいと思ったならば、「人様にお見せするものでは……」などという謙譲精神とはオサラバし、自分の人生はつまらない平凡なものという誤認識もきれいさっぱり捨てて、あなたらしい人生の一幕にかっと目を啓き(ひらき)ましょう。前述のように、人生に同じものはひとつとしてなく、ドラマのない人生もあり得ません。生の証として残されるものだからこそ、自分の真実の歴史を描くためにいっそうの気構えをもって臨むべきでしょう。畢竟、「自分史」とは、あなたがただひとりの主人公である物語なのですから。
※Amazonのアソシエイトとして、文芸社は適格販売により収入を得ています。
2024/08/23
3
いま私小説を書くなら「露悪」や「破滅」は忘れておきたい 以前、当ブログ記事『「小説」をいかに読み、いかに書くか』では、“私小説を制する ...
2023/11/21
3
「ベタぼれ」でいい、けれどそれだけではもの足りない 犬ってかわいいですよね。もちろん犬だけではありません。「猫可愛がり」なんて言葉が辞 ...
2023/06/19
3
小説を書くのは小説を読んだから──の回答に秘められた重要な鍵 いきなりですが、あなたがもし「小説家になりたい!」と日夜創作に向かってい ...
2023/06/12
3
現代の徒然なる日記──ブログ そのむかし、人は秘められた思いを日記に綴ってきました。そう、大正・昭和の文学青年も、純情可憐な恋する少女 ...
2025/04/17
4
「死生観」──さて、あなたはどう描く? 日本人の「死生観」……なんていうとちょっと大仰になってしまうので、もっとシンプルにお訊きします ...
2025/04/04
5
ファンタジーと「エブリデイ・マジック」 古くは『ナルニア国物語』、現代でも『ハリー・ポッター』など、ひとたび火が点けば異次元のセールス ...
2025/03/11
5
「自由」って本当にいいもの? ひとくちに「自由」といっても、いろいろな形やイメージがあるわけですが、その根本的な意識・認識は時代ととも ...
2025/02/19
4
「恐怖」、それは底知れないもの 人間がもつ“人間らしさ”のひとつに、「感情」が挙げられます。動物にだって感情はあるワイ! というご意見 ...